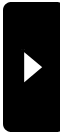2025年04月04日
お城めぐり!165城目【鹿児島城】
お城めぐりの165城目は、
鹿児島県鹿児島市にあります、鹿児島城!

言わずと知れた、薩摩・島津家の居城です。
西南戦争終焉の地でもあります。
国の史跡に指定、日本100名城にも選定されております。
鹿児島城へは2016年、前回の人吉城から鉄道で移動して、
鹿児島の夜を楽しみ、
翌日、指宿枕崎線を乗り鉄して向かいました。
その辺りの流れからになりまして、鹿児島城はかなり下の方で登場しますので、
流れが必要ない方は写真を55枚ほど下へスクロールして下さい(笑)
人吉駅から肥薩線(人吉駅と吉松駅間は2020年の豪雨により2025.4現在不通)に乗車し南下、
山間部を抜けます

矢岳駅でしばらく停車だったみたいで、矢岳駅を散策

2016年に行ったときは既に無人駅でしたが、昔は駅員さんもいて、切符も窓口で販売していたことが分かります。

現在は豪雨により不通ですが、当時の時刻表を見てもいずれ廃線になっていたかも?

古い木造駅舎は、とても良い雰囲気でした

ひっそりと人吉市SL展示館

矢岳と言えば、日本三大車窓の一つ、矢岳越え
雄大な景色が見れました

天気がイマイチだったのが「ちょっと残念・・・

吉松駅到着

右の赤いのが乗ってきたキハ220、左の白いのがこれから乗るキハ40

吉松駅でも時刻表チェック!肥薩線の人吉方面が圧倒的に本数が少ないですね。

これから乗るキハ40!この写真だけ見ると昭和ですね。

となりのホームにも都城方面行のキハ40。

行先案内もアナログの差し替え式

吉松駅から隼人駅へ向かいます

隼人駅到着

すっかり暗くなってました

乗り換え時間があったのかな?駅の外へ出たみたいです。
もう1度乗り換えしてよくやく鹿児島中央駅に到着

鹿児島中央駅!観覧車が夜の街に映えますね

早速ホテルでチェックイン!
レトロでチョットお洒落なホテルでした



早速夜の鹿児島散策
かごしま屋台村へ

雰囲気の良い路地と屋台が軒を連ねます


地鶏の刺身やさつま揚げをツマミながら1杯

隣に居合わせた方々と、写真を撮ってありますが、勝手に載せられないので掲載はとりあえずやめておきます。
楽しかった事だけは覚えてます。
締めのラーメン

素敵な屋台の数々でした

さりげない一言がいいですね~


次の日の列車が早いので早めに退散?
そして翌日、始発の指宿枕崎線に乗車
なんと4:51発!よく起きられたもんだ

山川駅行のキハ200

明るくなってきて車窓を楽しみながら向かいます

途中乗り換え

見えてきたのは特徴的な尖がった山、開聞岳が見えました


そして、日本最南端の駅(ゆいレールは除く)西大山駅



日本最南端の終着駅、枕崎駅到着!




これまた本数が少ないですね。7:32の指宿駅行で戻ります


鹿児島までは行かず、途中の喜入駅で下車

バスに乗車

向かったのは知覧特攻平和会館

本当はこの後、知覧城へ行く予定でしたが、平和会館があまりにも内容が濃すぎて離れられず・・・
結局、この私が知覧城をあきらめることに・・・(7年後にリベンジ出来ました!)
鹿児島へ戻り、お昼ごはんとしろくま目的で天文館へ
めちゃくちゃ並んでました



ステーキを食べ

デザートにしろくま

いよいよ鹿児島城へ
天文館から歩いて向かいました。
鶴丸城址前の信号あたりで石垣が見えてきます

城山町7が目につきます


堀と石垣

本丸を守る堀と石垣が続きます

そして本丸へ。行った頃は本丸の一部を整備改修工事をしていました


島津斉彬の養女となり、徳川13代将軍徳川家定に嫁いだ、篤姫こと天璋院の銅像

そして本丸にある鹿児島県歴史資料センター黎明館へ
薩摩の中世城郭分布図

中でもその後、続日本100名城となる志布志城もしっかり案内

模型のインパクトは今でも覚えてます。

そして本丸敷地の歴史について

本丸御殿模型。右下の御楼門は現在復元されてます

そして御楼門跡へ向かいます

門らしい桝形が見えてきます


御楼門の石垣には西南戦争の銃弾の跡が見られます


桝形虎口です



広い虎口です

橋を渡り御楼門虎口と奥には黎明館

門を抜け、橋を渡ると鶴丸城跡碑が建ってます。

城址碑と橋と御楼門(復元前)

そして、2020年に復元された御楼門!2023年に訪れました。

残念ながら正月に行ったので、門の中へは入れず

本丸内部から見た御楼門


橋と御楼門

御楼門説明


鶴丸城の説明


2023年に訪れた時は西南戦争時に西郷隆盛が籠って、最期を迎えた、鹿児島城背後の城山へも行きました

本丸西側から登る城山遊歩道は整備されており歩きやすかったです

20分から30分くらいだったかで城山展望台到着


桜島が目の前に見えます!雄大だ!

鹿児島中央駅方面

観光案内図

城山を東側から下りたところにも城址碑

本丸東側の堀と本丸へ続く橋

時を戻し2016年訪問時
本丸東側堀は蓮の花が沢山咲いていました。夕方だったのできれいに咲いている蓮は見れませんでしたが・・・


そして、かつての鹿児島の中心駅だった、鹿児島駅へ

鹿児島駅から路面電車に乗って鹿児島中央駅へ

次の目的地へ向かうのでありました。
そんな訳で次回のお城めぐり166城目は佐敷城です
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
鹿児島県鹿児島市にあります、鹿児島城!

言わずと知れた、薩摩・島津家の居城です。
西南戦争終焉の地でもあります。
国の史跡に指定、日本100名城にも選定されております。
鹿児島城へは2016年、前回の人吉城から鉄道で移動して、
鹿児島の夜を楽しみ、
翌日、指宿枕崎線を乗り鉄して向かいました。
その辺りの流れからになりまして、鹿児島城はかなり下の方で登場しますので、
流れが必要ない方は写真を55枚ほど下へスクロールして下さい(笑)
人吉駅から肥薩線(人吉駅と吉松駅間は2020年の豪雨により2025.4現在不通)に乗車し南下、
山間部を抜けます

矢岳駅でしばらく停車だったみたいで、矢岳駅を散策

2016年に行ったときは既に無人駅でしたが、昔は駅員さんもいて、切符も窓口で販売していたことが分かります。

現在は豪雨により不通ですが、当時の時刻表を見てもいずれ廃線になっていたかも?

古い木造駅舎は、とても良い雰囲気でした

ひっそりと人吉市SL展示館

矢岳と言えば、日本三大車窓の一つ、矢岳越え
雄大な景色が見れました

天気がイマイチだったのが「ちょっと残念・・・

吉松駅到着

右の赤いのが乗ってきたキハ220、左の白いのがこれから乗るキハ40

吉松駅でも時刻表チェック!肥薩線の人吉方面が圧倒的に本数が少ないですね。

これから乗るキハ40!この写真だけ見ると昭和ですね。

となりのホームにも都城方面行のキハ40。

行先案内もアナログの差し替え式

吉松駅から隼人駅へ向かいます

隼人駅到着

すっかり暗くなってました

乗り換え時間があったのかな?駅の外へ出たみたいです。
もう1度乗り換えしてよくやく鹿児島中央駅に到着

鹿児島中央駅!観覧車が夜の街に映えますね

早速ホテルでチェックイン!
レトロでチョットお洒落なホテルでした



早速夜の鹿児島散策
かごしま屋台村へ

雰囲気の良い路地と屋台が軒を連ねます


地鶏の刺身やさつま揚げをツマミながら1杯

隣に居合わせた方々と、写真を撮ってありますが、勝手に載せられないので掲載はとりあえずやめておきます。
楽しかった事だけは覚えてます。
締めのラーメン

素敵な屋台の数々でした

さりげない一言がいいですね~


次の日の列車が早いので早めに退散?
そして翌日、始発の指宿枕崎線に乗車
なんと4:51発!よく起きられたもんだ

山川駅行のキハ200

明るくなってきて車窓を楽しみながら向かいます

途中乗り換え

見えてきたのは特徴的な尖がった山、開聞岳が見えました


そして、日本最南端の駅(ゆいレールは除く)西大山駅



日本最南端の終着駅、枕崎駅到着!




これまた本数が少ないですね。7:32の指宿駅行で戻ります


鹿児島までは行かず、途中の喜入駅で下車

バスに乗車

向かったのは知覧特攻平和会館

本当はこの後、知覧城へ行く予定でしたが、平和会館があまりにも内容が濃すぎて離れられず・・・
結局、この私が知覧城をあきらめることに・・・(7年後にリベンジ出来ました!)
鹿児島へ戻り、お昼ごはんとしろくま目的で天文館へ
めちゃくちゃ並んでました



ステーキを食べ

デザートにしろくま

いよいよ鹿児島城へ
天文館から歩いて向かいました。
鶴丸城址前の信号あたりで石垣が見えてきます

城山町7が目につきます


堀と石垣

本丸を守る堀と石垣が続きます

そして本丸へ。行った頃は本丸の一部を整備改修工事をしていました


島津斉彬の養女となり、徳川13代将軍徳川家定に嫁いだ、篤姫こと天璋院の銅像

そして本丸にある鹿児島県歴史資料センター黎明館へ
薩摩の中世城郭分布図

中でもその後、続日本100名城となる志布志城もしっかり案内

模型のインパクトは今でも覚えてます。

そして本丸敷地の歴史について

本丸御殿模型。右下の御楼門は現在復元されてます

そして御楼門跡へ向かいます

門らしい桝形が見えてきます


御楼門の石垣には西南戦争の銃弾の跡が見られます


桝形虎口です



広い虎口です

橋を渡り御楼門虎口と奥には黎明館

門を抜け、橋を渡ると鶴丸城跡碑が建ってます。

城址碑と橋と御楼門(復元前)

そして、2020年に復元された御楼門!2023年に訪れました。

残念ながら正月に行ったので、門の中へは入れず

本丸内部から見た御楼門


橋と御楼門

御楼門説明


鶴丸城の説明


2023年に訪れた時は西南戦争時に西郷隆盛が籠って、最期を迎えた、鹿児島城背後の城山へも行きました

本丸西側から登る城山遊歩道は整備されており歩きやすかったです

20分から30分くらいだったかで城山展望台到着


桜島が目の前に見えます!雄大だ!

鹿児島中央駅方面

観光案内図

城山を東側から下りたところにも城址碑

本丸東側の堀と本丸へ続く橋

時を戻し2016年訪問時
本丸東側堀は蓮の花が沢山咲いていました。夕方だったのできれいに咲いている蓮は見れませんでしたが・・・


そして、かつての鹿児島の中心駅だった、鹿児島駅へ

鹿児島駅から路面電車に乗って鹿児島中央駅へ

次の目的地へ向かうのでありました。
そんな訳で次回のお城めぐり166城目は佐敷城です
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2025年02月28日
お城めぐり!164城目【人吉城】
お城めぐりの164城目は、
熊本県人吉市の人吉城です。

人吉城は相良氏が鎌倉時代から幕末まで在城。
相良と言えば、私は遠江の相良城を思い出しますが、
相良氏は鎌倉時代に遠江国の相良(現在の牧之原市)から人吉荘へ地頭として赴任したそうです。
実際に人吉城へ行くまで知りませんでした。
人吉城は国の史跡に指定され、日本100名城にも選定されております。
その人吉城へは、平成28年4月熊本地震が起こった夏に災害復旧のボランディアとして行った、ついでの城めぐりで訪れました。
ちなみに人吉城の1つ前の城は、前回の八代城です。
前日に八代城を見た後に、人吉とは反対の熊本まで戻り熊本駅前のホテルへ泊まりましたが、
理由はSL人吉号に乗る為です。
そんな訳で、まだ改装工事中の熊本駅へ
ちなみに、人吉城はまだかなり先に登場にて、鉄道に興味が無い方はスクロール↓してください。
※写真50枚分くらいは先です
高架のホームは既に新しくなっておりました。

ホームの柱廻りや屋根の小屋組みだけでなく、ベンチまで木製なのがJR九州っぽいですね

SL人吉の入線も見ようと早めに駅にへ来るも、
1時間以上も前に来てしまったので、

先に出発する「いさぶろう号」が偶然にも入線。

いさぶろう号は熊本駅発・吉松駅行で、
逆の吉松駅発・熊本駅行が「しんぺい号」となるので、
列車自体の表記は「いさぶろう・しんぺい」となっています。


出発するまで中を少し散策

のりば案内

残念がら「いさぶろう・しんぺい」も「SL人吉」も近年運行終了となっていますので、
今となっては貴重な乗車となってしまいました。
SL人吉がディーゼル機関車に引かれて入線

ディーゼル機関車はお役御免で切り離されて、

先頭には蒸気機関車

大井川鉄道、SLばんえつ物語、SLやまぐちに続き、人生4度目のSL(明治村のSLと京都鉄道博物館のSLは除きます)でしたが、やはりカッコイイ!

客車にSL人吉の文字があちこちに表記


車掌室

最後尾の展望デッキ車両

4人BOXシートですが、先に一人分を確保。結局、私の前も予約された方がお二人いましたが、ずっと展望席かどこかに行かれていた様で、ほぼ一人で楽しんでしまいました。

出発前にゾロゾロと乗ってきました

熊本駅を出発!うっすら煙が見えます


車内を早速散策。
中はレトロ感満載

模型や沿線の案内スペースもありました


SL文庫なる本棚も

そして展望デッキ

ありがたい売店、CAFE & BAR

地ビールとつまみに辛子レンコン

街からだんだん長閑な風景に

昨日来た八代駅到着

こちらでは停車時間がながかったのか、ホームに降りて撮影したみたいです(記憶にない)



釜へ石炭を入れるシーンが上手く撮影できていました

まもなく出発の合図として毎駅乗務員さんが鐘を鳴らしてくれました

途中で記念時乗車証が配布されました

球磨川沿いを走るので、山と川の素敵な景色が見れます


電車旅の醍醐味の一つはお酒が飲めること

アイスも追加でいただきました

途中、一勝地駅でも見学時間様に数分停車

地元の方もお土産へ販売で待ち構えてます。

一勝地駅舎

駅舎前からの球磨川

案内看板

他数駅でも同じように停車、そして、人吉駅到着
下りる前に人であふれていた展望デッキへ

人吉駅に到着したSL人吉と、八代駅行の普通電車

最初で最後となってしまったSL人吉ですが、その前に2025年2月現在、肥薩線自体が数年前の九州豪雨による球磨川氾濫で不通にてはやく復旧して欲しいですね。

人吉駅で、おじさんが鮎寿司を首から下げて売っていたので

思わず勢いで購入

早速駅のベンチでいただきました

駅前ロータリー横の広場には城郭建築風時計がありました。

駅舎もシックイの白壁風建築で、雰囲気は統一されていました

歩いて人吉城へ向かいます。
球磨川

途中、武家屋敷があり、人吉城から移築された堀合門があり、人吉城で唯一現存する建造物だそうです。


多門櫓が見えてきました

多門櫓から塀が続き、櫓・塀を支える石垣もキレイに見えます


橋の反対側にも石垣が続きます


橋を渡りきると大手門がありました


川へ下ります

多門櫓下には犬走りがあり奥まで歩けそうです

橋の下も石垣がしっかり残ってます

大手門を抜けると城内へ。多門櫓の入口にご自由にご覧くださいと案内が

もちろん中へ


絵図

人吉城の模型。右下の橋を渡った先の門が大手門で大手門の左手が多門櫓です。武家屋敷の奥に、御殿、その上に本丸があります。

平山部分が本丸・二の丸・三の丸

多門櫓を出て、正面に現れる広いスペースは模型の通りかつて武家屋敷がありました。奥の小高い山が人吉城の主郭部分です。

礎石で武家屋敷跡を表現

武家屋敷の一部。渋谷家屋敷跡

井戸


奥にある建物、人吉歴史館へ
こちらで日本100名城のスタンプを押し、
復元された武家屋敷の地下室へ



今はあるか分かりませんが、相良の殿様の顔出しパネル

人吉城案内

別の案内

大台所と御厩跡も

大きさが分かるように整備されています

さて、本丸のある東方面へ

藩主の屋敷があった御館の石垣

中へ

現在は相良神社があります

御館跡には庭園が残されてあり、しっかり整備されております

御館跡庭園の説明看板

御館南堀にかかる橋

御館南堀と石垣


更に東へ

上ります

更に長い階段を上ります

上がりきると三の丸の石垣が行く手を阻むように現れます


見下ろすと御館跡(相良神社)

人吉駅方面

三の丸へ向かいます

三の丸の石垣の奥の高台は二の丸

三の丸虎口は二の丸の石垣の前を通ることになります

右手には三の丸石垣が続きます

虎口を抜け右手には広い三の丸が見渡せます

三の丸から見た二の丸石垣

三の丸石碑

少し戻り虎口を抜けた左手は二の丸石垣が伸びております

途中の階段から二の丸へ入れそうですが、階段はスルーして

三の丸から二の丸へ続く中の御門から攻めます

桝形です

門の廻りの石垣は高く、本来は石垣の上に櫓門や塀が建っていたのでかなりの高さだったかと

中の御門の中へ

門から三の丸方面を振り返る

二の丸

二の丸石碑

右手奥が本丸

二の丸案内

スルーして上らなかった階段、下りると三の丸へ

本丸へ向かいます

本丸到着

本丸案内。天守は建てられず、護摩堂や太鼓屋、山伏番所があったそうです。

本丸石碑

建物があった礎石があちらこちらにあります

中の御門へ戻り

そのまま北側から下ります

下りると球磨川が見えてきます。手前の石垣は御下門

下りてきた階段

御下門の石垣は高いくて威圧感があります

御下門説明

米蔵跡

堀合門と奥に続く石垣

堀合門は来る途中に見た武家屋敷に移築された堀合門があったので、こちらが復元ですね

人吉城址碑

こちらが人吉城と言えば!の石垣上部にある出っ張り石、「武者返し」


石垣の下にはしっかり側溝もあります

武者返し石垣は途中で折れますが長く続いております

武者返し案内

堀合門の目の前には球磨川と接する水の手門があります

水の手門説明

こちらからは船が着けられ、球磨川を利用して物資などをを運び入れたりしたのでしょうね

水門から武者返し石垣を見る。石垣の防御力が高く、とても攻められそうにない

こちらにも人吉城の案内があります

左手は米蔵、左手奥は水の手門、右手は武者返し石垣

最後にしっかり武者返しを目に焼き付けました




そのまま球磨川沿いを西へ戻り、復元されta角櫓へ

角櫓案内

最後に本丸方面を望む

人吉駅に戻り、次の列車まで時間があったので隣接する人吉鉄道ミュージアムへ

中にはJR九州の列車と運行ルート図や

ミニSLが走ってました


売店にはなんと「武者返し」なる焼酎が

古い車庫です

かつてはにぎわっていただろう人吉駅。何本もあった線路の跡が見られます。

2025年2月現在、JR肥薩線は不通ですが、くま川鉄道は動いているようです
到着した時はここに、SL人吉号と八代行普通電車が並んでました

よく見る工芸品がホームにも

雰囲気のある1番線ホーム

時間が無くて乗り鉄出来なかったくま川鉄道


私が乗る吉松行普通電車が入線

時を同じく朝、熊本駅で見送った、「しんぺい号」が吉松から人吉に戻ってきました

今はもう走ってないので、こちらの看板も無いでしょうね・・・

私が乗った普通電車ですが、流石はJR九州の車両です、木を使った座席や展望スペースもありました



この後は、人吉駅から普通電車に車窓を楽しみながら、鹿児島入りするのでありました。
そんな訳で、次回165城目は鹿児島城です!
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
熊本県人吉市の人吉城です。

人吉城は相良氏が鎌倉時代から幕末まで在城。
相良と言えば、私は遠江の相良城を思い出しますが、
相良氏は鎌倉時代に遠江国の相良(現在の牧之原市)から人吉荘へ地頭として赴任したそうです。
実際に人吉城へ行くまで知りませんでした。
人吉城は国の史跡に指定され、日本100名城にも選定されております。
その人吉城へは、平成28年4月熊本地震が起こった夏に災害復旧のボランディアとして行った、ついでの城めぐりで訪れました。
ちなみに人吉城の1つ前の城は、前回の八代城です。
前日に八代城を見た後に、人吉とは反対の熊本まで戻り熊本駅前のホテルへ泊まりましたが、
理由はSL人吉号に乗る為です。
そんな訳で、まだ改装工事中の熊本駅へ
ちなみに、人吉城はまだかなり先に登場にて、鉄道に興味が無い方はスクロール↓してください。
※写真50枚分くらいは先です
高架のホームは既に新しくなっておりました。

ホームの柱廻りや屋根の小屋組みだけでなく、ベンチまで木製なのがJR九州っぽいですね

SL人吉の入線も見ようと早めに駅にへ来るも、
1時間以上も前に来てしまったので、

先に出発する「いさぶろう号」が偶然にも入線。

いさぶろう号は熊本駅発・吉松駅行で、
逆の吉松駅発・熊本駅行が「しんぺい号」となるので、
列車自体の表記は「いさぶろう・しんぺい」となっています。


出発するまで中を少し散策

のりば案内

残念がら「いさぶろう・しんぺい」も「SL人吉」も近年運行終了となっていますので、
今となっては貴重な乗車となってしまいました。
SL人吉がディーゼル機関車に引かれて入線

ディーゼル機関車はお役御免で切り離されて、

先頭には蒸気機関車

大井川鉄道、SLばんえつ物語、SLやまぐちに続き、人生4度目のSL(明治村のSLと京都鉄道博物館のSLは除きます)でしたが、やはりカッコイイ!

客車にSL人吉の文字があちこちに表記


車掌室

最後尾の展望デッキ車両

4人BOXシートですが、先に一人分を確保。結局、私の前も予約された方がお二人いましたが、ずっと展望席かどこかに行かれていた様で、ほぼ一人で楽しんでしまいました。

出発前にゾロゾロと乗ってきました

熊本駅を出発!うっすら煙が見えます


車内を早速散策。
中はレトロ感満載

模型や沿線の案内スペースもありました


SL文庫なる本棚も

そして展望デッキ

ありがたい売店、CAFE & BAR

地ビールとつまみに辛子レンコン

街からだんだん長閑な風景に

昨日来た八代駅到着

こちらでは停車時間がながかったのか、ホームに降りて撮影したみたいです(記憶にない)



釜へ石炭を入れるシーンが上手く撮影できていました

まもなく出発の合図として毎駅乗務員さんが鐘を鳴らしてくれました

途中で記念時乗車証が配布されました

球磨川沿いを走るので、山と川の素敵な景色が見れます


電車旅の醍醐味の一つはお酒が飲めること

アイスも追加でいただきました

途中、一勝地駅でも見学時間様に数分停車

地元の方もお土産へ販売で待ち構えてます。

一勝地駅舎

駅舎前からの球磨川

案内看板

他数駅でも同じように停車、そして、人吉駅到着
下りる前に人であふれていた展望デッキへ

人吉駅に到着したSL人吉と、八代駅行の普通電車

最初で最後となってしまったSL人吉ですが、その前に2025年2月現在、肥薩線自体が数年前の九州豪雨による球磨川氾濫で不通にてはやく復旧して欲しいですね。

人吉駅で、おじさんが鮎寿司を首から下げて売っていたので

思わず勢いで購入

早速駅のベンチでいただきました

駅前ロータリー横の広場には城郭建築風時計がありました。

駅舎もシックイの白壁風建築で、雰囲気は統一されていました

歩いて人吉城へ向かいます。
球磨川

途中、武家屋敷があり、人吉城から移築された堀合門があり、人吉城で唯一現存する建造物だそうです。


多門櫓が見えてきました

多門櫓から塀が続き、櫓・塀を支える石垣もキレイに見えます


橋の反対側にも石垣が続きます


橋を渡りきると大手門がありました


川へ下ります

多門櫓下には犬走りがあり奥まで歩けそうです

橋の下も石垣がしっかり残ってます

大手門を抜けると城内へ。多門櫓の入口にご自由にご覧くださいと案内が

もちろん中へ


絵図

人吉城の模型。右下の橋を渡った先の門が大手門で大手門の左手が多門櫓です。武家屋敷の奥に、御殿、その上に本丸があります。

平山部分が本丸・二の丸・三の丸

多門櫓を出て、正面に現れる広いスペースは模型の通りかつて武家屋敷がありました。奥の小高い山が人吉城の主郭部分です。

礎石で武家屋敷跡を表現

武家屋敷の一部。渋谷家屋敷跡

井戸


奥にある建物、人吉歴史館へ
こちらで日本100名城のスタンプを押し、
復元された武家屋敷の地下室へ



今はあるか分かりませんが、相良の殿様の顔出しパネル

人吉城案内

別の案内

大台所と御厩跡も

大きさが分かるように整備されています

さて、本丸のある東方面へ

藩主の屋敷があった御館の石垣

中へ

現在は相良神社があります

御館跡には庭園が残されてあり、しっかり整備されております

御館跡庭園の説明看板

御館南堀にかかる橋

御館南堀と石垣


更に東へ

上ります

更に長い階段を上ります

上がりきると三の丸の石垣が行く手を阻むように現れます


見下ろすと御館跡(相良神社)

人吉駅方面

三の丸へ向かいます

三の丸の石垣の奥の高台は二の丸

三の丸虎口は二の丸の石垣の前を通ることになります

右手には三の丸石垣が続きます

虎口を抜け右手には広い三の丸が見渡せます

三の丸から見た二の丸石垣

三の丸石碑

少し戻り虎口を抜けた左手は二の丸石垣が伸びております

途中の階段から二の丸へ入れそうですが、階段はスルーして

三の丸から二の丸へ続く中の御門から攻めます

桝形です

門の廻りの石垣は高く、本来は石垣の上に櫓門や塀が建っていたのでかなりの高さだったかと

中の御門の中へ

門から三の丸方面を振り返る

二の丸

二の丸石碑

右手奥が本丸

二の丸案内

スルーして上らなかった階段、下りると三の丸へ

本丸へ向かいます

本丸到着

本丸案内。天守は建てられず、護摩堂や太鼓屋、山伏番所があったそうです。

本丸石碑

建物があった礎石があちらこちらにあります

中の御門へ戻り

そのまま北側から下ります

下りると球磨川が見えてきます。手前の石垣は御下門

下りてきた階段

御下門の石垣は高いくて威圧感があります

御下門説明

米蔵跡

堀合門と奥に続く石垣

堀合門は来る途中に見た武家屋敷に移築された堀合門があったので、こちらが復元ですね

人吉城址碑

こちらが人吉城と言えば!の石垣上部にある出っ張り石、「武者返し」


石垣の下にはしっかり側溝もあります

武者返し石垣は途中で折れますが長く続いております

武者返し案内

堀合門の目の前には球磨川と接する水の手門があります

水の手門説明

こちらからは船が着けられ、球磨川を利用して物資などをを運び入れたりしたのでしょうね

水門から武者返し石垣を見る。石垣の防御力が高く、とても攻められそうにない

こちらにも人吉城の案内があります

左手は米蔵、左手奥は水の手門、右手は武者返し石垣

最後にしっかり武者返しを目に焼き付けました




そのまま球磨川沿いを西へ戻り、復元されta角櫓へ

角櫓案内

最後に本丸方面を望む

人吉駅に戻り、次の列車まで時間があったので隣接する人吉鉄道ミュージアムへ

中にはJR九州の列車と運行ルート図や

ミニSLが走ってました


売店にはなんと「武者返し」なる焼酎が

古い車庫です

かつてはにぎわっていただろう人吉駅。何本もあった線路の跡が見られます。

2025年2月現在、JR肥薩線は不通ですが、くま川鉄道は動いているようです
到着した時はここに、SL人吉号と八代行普通電車が並んでました

よく見る工芸品がホームにも

雰囲気のある1番線ホーム

時間が無くて乗り鉄出来なかったくま川鉄道


私が乗る吉松行普通電車が入線

時を同じく朝、熊本駅で見送った、「しんぺい号」が吉松から人吉に戻ってきました

今はもう走ってないので、こちらの看板も無いでしょうね・・・

私が乗った普通電車ですが、流石はJR九州の車両です、木を使った座席や展望スペースもありました



この後は、人吉駅から普通電車に車窓を楽しみながら、鹿児島入りするのでありました。
そんな訳で、次回165城目は鹿児島城です!
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2025年02月06日
お城めぐり!163城目【八代城】
お城めぐりの163城目は、
熊本県八代市にあります、八代城

八代城は同じ肥後の国に熊本城があるにもかかわらず、一国一城令の例外として江戸幕府に一国二城が認められたお城です。
国の史跡に指定、続日本100名城にも選定されております。
その八代城へ行ったのは8年前。
前回の宇土城の後に訪れました。
鹿児島本線の八代駅で下車


九州新幹線開通後に鹿児島本線の八代から川内間は肥薩おれんじ鉄道となったので、こちらの駅舎(元々JR九州の建物だったと思いますが)

バスで市役所へ!
八代市役所の西側に八代城がありますが、その八代市役所もかつての八代城二の丸にありますので、市役所に着いた時点で、既に城の中に居たわけです。
現在残っている主な遺構は本丸を中心とした堀や石垣です。

二の丸から本丸へ続く橋を渡ります

橋から見た堀


橋を渡ると桝形の高麗門


桝形虎口にて石垣に囲まれた空間です


そして右へ折れます

渡ってきた橋方面

本丸東から入ってきまして、本丸北の方へ向かいます。
石垣と石垣の間に 埋み門がありました


埋み門を抜け右へ折れると廊下橋門へ続きます



こちらも熊本地震の影響で石垣が崩れていました。現在は積み直されているかもしれません。

廊下橋門を抜け本丸北側の石垣と堀


高くて重厚な石垣にうっとり・・・

そして細川忠興が隠居していた北の丸へ
現在は松井神社があります

松井神社には庭園や

細川忠興が植えたと伝えられている臥龍梅があります


本丸へ戻ります。また廊下橋門を抜けます

天守台の石垣を本丸内部から見上げます

こちらは小天守石垣

天守と小天守の間に上れそうな階段後が見えたので

上ってみると行き止まりでした・・・残念ながら天守台へはこちらから行けず・・・よじ登れば行けますけどね。

八代宮の廻りを抜けtる途中に井戸跡が


そして本丸南の石垣に上ります

現在は橋が架かりますが、当時は橋も門もなく、反対側の石垣と繋がっていた様です
そのまま石垣の上を南から南西の角へ向かいます

南西の角は月見櫓跡


柱が建っていただろう礎石がしっかり残っています


月見櫓からそのまま北へ

下から上がれなかった小天守

先程上がってきた階段。簡単に矢を射られてやられていたかと。

八代宮の社が見えます

小天守の先には天守台がチラリ

天守台へ

中は石垣に囲まれているので、穴蔵となっております。

階段があるので天守台に登れました

天守台はやはり高い
天皇陛下もこちらから眺めたみたいです。きっと昭和天皇ですね。

天守台を下ります

天守台のある本丸北西から本丸南側へ戻ります

切れていた本丸南石垣の東側へ上がります

まっすぐ奥が月見櫓

東の方へぐるりと


高低差のある見事な高石垣と水堀です

舞台脇の櫓跡?ってなんだ?って思いましたが

現在は脇と言いますか、櫓跡下に土俵があります。当時は能舞台があったそうです。

更に東へ向かい東南の隅へ

東南の隅は、宝形櫓跡

東側には二の丸。今は市役所があります

本丸東側石垣。最初に渡ってきた高麗門へ続く橋が見えます

石垣を下り、土俵を抜け

本丸中央にある八代宮へ


当時はなかった本丸南側の橋あたりにあった案内看板

堂々の国の史跡

国の史跡になる前は、県の史跡

現地にあった鳥観図。一の門から橋が伸びているのが現在の形です

どの段階で橋が架けられたか分かりませんが、違和感ありません。

この堀越しに見る手前角の月見櫓跡から奥の天守台の石垣素敵です!

堀が広くて橋も石垣も映える!

本丸西側にある八代市立博物館未来の森のミュージアムへ。特別展もやっていたみたい。記憶にない・・・

個性的な建物もかっこいい!


中へ入ると八代城の模型に

縄張り図

自分が見てきたルートや石垣を確認。ここで南側に橋がなかった事に気づくのでありました
当時はまだ続日本100名城選定前でしたので、スタンプラリーもやってないのですが、
現在はこちらの博物館で押せるみたいです。
最後に天守台石垣を目に焼き付けて!

市役所のバス停へ戻ります。流石市役所、沢山バスが走ってますので、あまり考えずともバスがやってきます。確か。

八代駅に戻ります。
反対側ホームにはキハ40

熊本行普通に乗り込み

車窓を眺めながら熊本まで

次の日は朝からあれに乗って人吉城へ向かうので、熊本駅近くのホテルに泊まりました。
部屋から見る熊本駅。現在はさらに改装されこちらの景色と全然違うと思います。

晩御飯は熊本名物セット!だご汁、馬刺し、辛子レンコン!

そんな訳で、久々に長い長い内容の、八代城でした。
続日本100名城のスタンプを押しにまた行かねばなりません!
また行く理由が出来て嬉しいです(笑)
次回164城目は人吉城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
熊本県八代市にあります、八代城

八代城は同じ肥後の国に熊本城があるにもかかわらず、一国一城令の例外として江戸幕府に一国二城が認められたお城です。
国の史跡に指定、続日本100名城にも選定されております。
その八代城へ行ったのは8年前。
前回の宇土城の後に訪れました。
鹿児島本線の八代駅で下車


九州新幹線開通後に鹿児島本線の八代から川内間は肥薩おれんじ鉄道となったので、こちらの駅舎(元々JR九州の建物だったと思いますが)

バスで市役所へ!
八代市役所の西側に八代城がありますが、その八代市役所もかつての八代城二の丸にありますので、市役所に着いた時点で、既に城の中に居たわけです。
現在残っている主な遺構は本丸を中心とした堀や石垣です。

二の丸から本丸へ続く橋を渡ります

橋から見た堀


橋を渡ると桝形の高麗門


桝形虎口にて石垣に囲まれた空間です


そして右へ折れます

渡ってきた橋方面

本丸東から入ってきまして、本丸北の方へ向かいます。
石垣と石垣の間に 埋み門がありました


埋み門を抜け右へ折れると廊下橋門へ続きます



こちらも熊本地震の影響で石垣が崩れていました。現在は積み直されているかもしれません。

廊下橋門を抜け本丸北側の石垣と堀


高くて重厚な石垣にうっとり・・・

そして細川忠興が隠居していた北の丸へ
現在は松井神社があります

松井神社には庭園や

細川忠興が植えたと伝えられている臥龍梅があります


本丸へ戻ります。また廊下橋門を抜けます

天守台の石垣を本丸内部から見上げます

こちらは小天守石垣

天守と小天守の間に上れそうな階段後が見えたので

上ってみると行き止まりでした・・・残念ながら天守台へはこちらから行けず・・・よじ登れば行けますけどね。

八代宮の廻りを抜けtる途中に井戸跡が


そして本丸南の石垣に上ります

現在は橋が架かりますが、当時は橋も門もなく、反対側の石垣と繋がっていた様です
そのまま石垣の上を南から南西の角へ向かいます

南西の角は月見櫓跡


柱が建っていただろう礎石がしっかり残っています


月見櫓からそのまま北へ

下から上がれなかった小天守

先程上がってきた階段。簡単に矢を射られてやられていたかと。

八代宮の社が見えます

小天守の先には天守台がチラリ

天守台へ

中は石垣に囲まれているので、穴蔵となっております。

階段があるので天守台に登れました

天守台はやはり高い

天皇陛下もこちらから眺めたみたいです。きっと昭和天皇ですね。

天守台を下ります

天守台のある本丸北西から本丸南側へ戻ります

切れていた本丸南石垣の東側へ上がります

まっすぐ奥が月見櫓

東の方へぐるりと


高低差のある見事な高石垣と水堀です

舞台脇の櫓跡?ってなんだ?って思いましたが

現在は脇と言いますか、櫓跡下に土俵があります。当時は能舞台があったそうです。

更に東へ向かい東南の隅へ

東南の隅は、宝形櫓跡

東側には二の丸。今は市役所があります

本丸東側石垣。最初に渡ってきた高麗門へ続く橋が見えます

石垣を下り、土俵を抜け

本丸中央にある八代宮へ


当時はなかった本丸南側の橋あたりにあった案内看板

堂々の国の史跡

国の史跡になる前は、県の史跡

現地にあった鳥観図。一の門から橋が伸びているのが現在の形です

どの段階で橋が架けられたか分かりませんが、違和感ありません。

この堀越しに見る手前角の月見櫓跡から奥の天守台の石垣素敵です!

堀が広くて橋も石垣も映える!

本丸西側にある八代市立博物館未来の森のミュージアムへ。特別展もやっていたみたい。記憶にない・・・

個性的な建物もかっこいい!


中へ入ると八代城の模型に

縄張り図

自分が見てきたルートや石垣を確認。ここで南側に橋がなかった事に気づくのでありました
当時はまだ続日本100名城選定前でしたので、スタンプラリーもやってないのですが、
現在はこちらの博物館で押せるみたいです。
最後に天守台石垣を目に焼き付けて!

市役所のバス停へ戻ります。流石市役所、沢山バスが走ってますので、あまり考えずともバスがやってきます。確か。

八代駅に戻ります。
反対側ホームにはキハ40

熊本行普通に乗り込み

車窓を眺めながら熊本まで

次の日は朝からあれに乗って人吉城へ向かうので、熊本駅近くのホテルに泊まりました。
部屋から見る熊本駅。現在はさらに改装されこちらの景色と全然違うと思います。

晩御飯は熊本名物セット!だご汁、馬刺し、辛子レンコン!

そんな訳で、久々に長い長い内容の、八代城でした。
続日本100名城のスタンプを押しにまた行かねばなりません!
また行く理由が出来て嬉しいです(笑)
次回164城目は人吉城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2024年12月09日
お城めぐり!162城目【宇土城(近世)】
お城めぐりの162城目は、
熊本県宇土市にある、宇土城(近世)!

前回の宇土古城に続き、今回は宇土城(近世)。
宇土城(近世)は小西行長が、宇土古城近くの城山に新しく築いた城です。
宇土古城から数分で宇土城(近世)


案内看板



宇土城址碑

西側から本丸へ通じる階段

本丸

私が行ったときは本丸でゲートボールをやっていました
少し古い説明看板

本丸から宇土古城を振り返り見ると、チラッと復元門が見えます。

宇土城と言えば、小西行長

熊本地震からまだ数か月にて、おそらく地震の影響で支柱に張られた石が剥がれ落ちていました。その影響で立入禁止。

流石に今は直してあると思いますが。

小西行長の案内

本丸東の腰曲輪?帯曲輪?

更に1段下がった本丸東

本丸東の石垣


本丸北西の石垣


そのまま北へ。民家の間の道を抜け出ることが出来ます

振り返り、正面は本丸

ここからは余談ですが
宇土駅に戻る途中、熊本地震の影響を受けた建物が多くありました。




宇土駅へ戻り

ホームへ

三角線を乗り鉄

三角線の景観を楽しみながら


終点の三角駅で、折り返し

特急「A列車で行こう」が入線しましたが、残念ながら18切符では乗れないのでスルー

いつかは乗ってみたい

帰りも車窓を楽しみながら

独特な浅瀬の形状

宇土駅へ戻り、次は八代城を目指すのでありました。
そんな訳で、次回163城目は八代城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
熊本県宇土市にある、宇土城(近世)!

前回の宇土古城に続き、今回は宇土城(近世)。
宇土城(近世)は小西行長が、宇土古城近くの城山に新しく築いた城です。
宇土古城から数分で宇土城(近世)


案内看板



宇土城址碑

西側から本丸へ通じる階段

本丸

私が行ったときは本丸でゲートボールをやっていました
少し古い説明看板

本丸から宇土古城を振り返り見ると、チラッと復元門が見えます。

宇土城と言えば、小西行長

熊本地震からまだ数か月にて、おそらく地震の影響で支柱に張られた石が剥がれ落ちていました。その影響で立入禁止。

流石に今は直してあると思いますが。

小西行長の案内

本丸東の腰曲輪?帯曲輪?

更に1段下がった本丸東

本丸東の石垣


本丸北西の石垣


そのまま北へ。民家の間の道を抜け出ることが出来ます

振り返り、正面は本丸

ここからは余談ですが
宇土駅に戻る途中、熊本地震の影響を受けた建物が多くありました。




宇土駅へ戻り

ホームへ

三角線を乗り鉄

三角線の景観を楽しみながら


終点の三角駅で、折り返し

特急「A列車で行こう」が入線しましたが、残念ながら18切符では乗れないのでスルー

いつかは乗ってみたい

帰りも車窓を楽しみながら

独特な浅瀬の形状

宇土駅へ戻り、次は八代城を目指すのでありました。
そんな訳で、次回163城目は八代城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2024年10月23日
お城めぐり!161城目【宇土古城】
お城めぐりの161城目は、
熊本県宇土市にある宇土古城です。

宇土古城になぜ古城が付くのか?
それは宇土城と区別するためです。
戦国時代に宇土古城から宇土城へ移築したので、
同じ宇土城なのですが、
移前と後では全く異なる城にて、今回は161城目の宇土古城、
次回は162城目の宇土城となります。
宇土古城は千畳敷と三城と呼ばれる2つの大きな曲輪で構成されておりました。
案内看板

まずは千畳敷から攻めました
千畳敷前の案内看板

下から千畳敷を見上げる。ぐるりと切岸で囲われております。

階段を上ると土塁を切った虎口と奥に再現された門が現れます

千畳敷の廻りはぐるりと掘が

崩れない様にモルタルで固められていました。これなら草も生えないし、見やすいですね。でもリアル感は薄れます。どちらが良いって訳ではありませんよ。

虎口へ向かいます

木柵もあり中世の城っぽい雰囲気

門を抜けると右に折れて千畳敷内へ

千畳敷にはいくつか建物の跡が確認されておりますが、そのうちの1棟が再現されていました


他の建物も背の低い柱で建物の位置を再現してあり、想像できるようになっていました

左手は入ってきた虎口

虎口横の建物跡(16号)


更に右手(北側)の建物跡(17号)


千畳敷の東側から

広い曲輪です

千畳敷からの景色


千畳敷から見た廻りの堀


堀の一部は未完成だったようです




上から見ると未完成かどうか良く分からないですが、工事の区分け跡が未完成の証拠の様です

堀に架かる橋も再現されていました


そして西側の三城へ

なにやら小屋に石が沢山置いてありました

発掘調査で出てきた石塔の石だそうです



曲輪の一部に石積が残っていました

三城にも建物がいくつかあったそうです


三城も広い曲輪でした

宇土古城を後にして宇土城へ。しっかり中世と近世と分けてあるので初めて来ても分かるように案内が出てます

近世宇土城近くから見た中世宇土古城。正面の丘が宇土古城

UPで見ると虎口の門が見えます

中世の城をしっかり感じることが出来る城でした。
よく整備されていることも見学者としてはありがたい限りです。
次回162城目は近世宇土城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
熊本県宇土市にある宇土古城です。

宇土古城になぜ古城が付くのか?
それは宇土城と区別するためです。
戦国時代に宇土古城から宇土城へ移築したので、
同じ宇土城なのですが、
移前と後では全く異なる城にて、今回は161城目の宇土古城、
次回は162城目の宇土城となります。
宇土古城は千畳敷と三城と呼ばれる2つの大きな曲輪で構成されておりました。
案内看板

まずは千畳敷から攻めました
千畳敷前の案内看板

下から千畳敷を見上げる。ぐるりと切岸で囲われております。

階段を上ると土塁を切った虎口と奥に再現された門が現れます

千畳敷の廻りはぐるりと掘が

崩れない様にモルタルで固められていました。これなら草も生えないし、見やすいですね。でもリアル感は薄れます。どちらが良いって訳ではありませんよ。

虎口へ向かいます

木柵もあり中世の城っぽい雰囲気

門を抜けると右に折れて千畳敷内へ

千畳敷にはいくつか建物の跡が確認されておりますが、そのうちの1棟が再現されていました


他の建物も背の低い柱で建物の位置を再現してあり、想像できるようになっていました

左手は入ってきた虎口

虎口横の建物跡(16号)


更に右手(北側)の建物跡(17号)


千畳敷の東側から

広い曲輪です

千畳敷からの景色


千畳敷から見た廻りの堀


堀の一部は未完成だったようです




上から見ると未完成かどうか良く分からないですが、工事の区分け跡が未完成の証拠の様です

堀に架かる橋も再現されていました


そして西側の三城へ

なにやら小屋に石が沢山置いてありました

発掘調査で出てきた石塔の石だそうです



曲輪の一部に石積が残っていました

三城にも建物がいくつかあったそうです


三城も広い曲輪でした

宇土古城を後にして宇土城へ。しっかり中世と近世と分けてあるので初めて来ても分かるように案内が出てます

近世宇土城近くから見た中世宇土古城。正面の丘が宇土古城

UPで見ると虎口の門が見えます

中世の城をしっかり感じることが出来る城でした。
よく整備されていることも見学者としてはありがたい限りです。
次回162城目は近世宇土城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2024年05月28日
お城めぐり!12城目【熊本城(その③)】
今回のお城めぐりは161城目ではなく、
12城目熊本城(その③)です。

1度目は本丸御殿が出来たころ
2度目は神谷部長と二人で行った社員旅行で。
今回の3回目は、2016年に熊本地震が起きた年のお盆休みにボランディア活動を兼ねて行きました。
※8年も前か・・・
お盆休み前の最終日に出陣
名古屋駅で博多行のぞみに乗り換え

博多駅で

熊本行のつばめに乗り換え



九州新幹線の車両のシートは普通席でも素晴らしいシート


熊本駅到着

くまもんがお出迎え

この日は直ぐにホテルへ向かい次の日に備えました

朝早く起床して、路面電車で熊本地震のボランティア活動の拠点、
熊本市災害ボランティアセンターへ

受付して

暑い中、片付け作業をさせていただきました。
くまもんと記念の撮影

ボランティア活動時にいただいたワッペン

こちらを見せると路面電車が無料で乗れるとの事で
時間があったので路面電車で熊本城へ向かいます

まずは毎回挨拶する加藤清正の銅像へ

早速、崩れた石垣が目に入る

塀も崩れシートがかけられていました

熊本城案内図

当然、中へは入れません

中には入れないが二の丸広場からは見られると

観光案内所やお土産屋などがある桜の馬場へ


お店で色んな話を伺い地震の恐怖や熊本城への愛着など熱いお話が聞けました。
まだ地震から4か月にて、お店を開けるの大変な方も多いようでしたが、早く復興をしたいとの想いから頑張って店をあけているとか。
8年前の話ですがしっかり記憶してます。
城彩苑では復興を願った展示物が



この熊本城天守

つまようじで描いてあるんです。凄い!

熊本地震で崩れた石垣の中から見つかった、石垣に描かれた落書き

熊本地震で天守最上階から落下した瓦


二の丸広場へ向かいます
途中、未申(ひつじさる)櫓を横目に

隣の堀に差し掛かると

石垣が塀ごと崩れたままになっているのを確認


二の丸駐車場にあるトイレも瓦が落ちて、赤紙が貼られ近づけない様になっていました

広い二の丸広場。

柵より先へは行けません。

天守が見えました!
右から大天守、小天守、そして左が私の好きな櫓である現存の宇土櫓

本来はこの辺りからも本丸方面に行けたはずです。
こちこちで、石垣に塀が崩れ、裏込め石も散乱


戌亥(いぬい)櫓の石垣や櫓に繋がる石垣も大部分が崩れてしまっています。

全く手が付けられていない場所もあれば

通路の安全確保の為に補強されているところも

それにしても酷い・・・


私個人的に熊本城で1番のビュースポットはこちら!宇土櫓とその後ろに大天守と小天守。宇土櫓の大きさは天守級です。

宇土櫓の下の堀はかなり深い事がよくわかります。

このスポットは清正公が祭られている加藤神社入口です


影響がなさそうな天守もよく見ると瓦が落ちて石垣も一部崩れ・・・現在は復興し見学できます。市長が肝入りで天守をいち早く復興させるって事で早く復興工事がなされました。他の箇所はまだまだですが・・・

宇土櫓も被害が無さそうですが、塀は崩れ外壁もハガレ、建物もただでさえ傾いていたのにさらに傾き、現在は中へ入ることが出来ず、いつ復旧が完了するかも未定だったかな?

最後に桜の馬場でお土産を購入

ちなみに熊本藩の藩校も吉田藩の藩校と同じ、時習館。まだ時習館は他の藩にもありますが割愛。

熊本城を後にします

復興後の天守へはまだ行ってないので、近いうちに行かねばなりませんが、行かなければならない城は山ほどありなかなか行けず・・・
路面電車で移動した先は

地元の居酒屋

地元の料理とビールで乾杯

自己満足でしょうが、ボランティア活動のついでに熊本城へ行き、
ホテルに泊まり、お土産を買い、地元で飲食をしてお金を落とすことが、個人的に出来る1番の復興活動と思ってます。
熊本城その3は、8年前の出来事を熊本地震に絡めてのご紹介となりました。
かなり脱線しましたが、それも城めぐり。
次回、161城目は宇土古城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
12城目熊本城(その③)です。

1度目は本丸御殿が出来たころ
2度目は神谷部長と二人で行った社員旅行で。
今回の3回目は、2016年に熊本地震が起きた年のお盆休みにボランディア活動を兼ねて行きました。
※8年も前か・・・
お盆休み前の最終日に出陣
名古屋駅で博多行のぞみに乗り換え

博多駅で

熊本行のつばめに乗り換え



九州新幹線の車両のシートは普通席でも素晴らしいシート


熊本駅到着

くまもんがお出迎え

この日は直ぐにホテルへ向かい次の日に備えました

朝早く起床して、路面電車で熊本地震のボランティア活動の拠点、
熊本市災害ボランティアセンターへ

受付して

暑い中、片付け作業をさせていただきました。
くまもんと記念の撮影

ボランティア活動時にいただいたワッペン

こちらを見せると路面電車が無料で乗れるとの事で
時間があったので路面電車で熊本城へ向かいます

まずは毎回挨拶する加藤清正の銅像へ

早速、崩れた石垣が目に入る

塀も崩れシートがかけられていました

熊本城案内図

当然、中へは入れません

中には入れないが二の丸広場からは見られると

観光案内所やお土産屋などがある桜の馬場へ


お店で色んな話を伺い地震の恐怖や熊本城への愛着など熱いお話が聞けました。
まだ地震から4か月にて、お店を開けるの大変な方も多いようでしたが、早く復興をしたいとの想いから頑張って店をあけているとか。
8年前の話ですがしっかり記憶してます。
城彩苑では復興を願った展示物が



この熊本城天守

つまようじで描いてあるんです。凄い!

熊本地震で崩れた石垣の中から見つかった、石垣に描かれた落書き

熊本地震で天守最上階から落下した瓦


二の丸広場へ向かいます
途中、未申(ひつじさる)櫓を横目に

隣の堀に差し掛かると

石垣が塀ごと崩れたままになっているのを確認


二の丸駐車場にあるトイレも瓦が落ちて、赤紙が貼られ近づけない様になっていました

広い二の丸広場。

柵より先へは行けません。

天守が見えました!
右から大天守、小天守、そして左が私の好きな櫓である現存の宇土櫓

本来はこの辺りからも本丸方面に行けたはずです。
こちこちで、石垣に塀が崩れ、裏込め石も散乱


戌亥(いぬい)櫓の石垣や櫓に繋がる石垣も大部分が崩れてしまっています。

全く手が付けられていない場所もあれば

通路の安全確保の為に補強されているところも

それにしても酷い・・・


私個人的に熊本城で1番のビュースポットはこちら!宇土櫓とその後ろに大天守と小天守。宇土櫓の大きさは天守級です。

宇土櫓の下の堀はかなり深い事がよくわかります。

このスポットは清正公が祭られている加藤神社入口です


影響がなさそうな天守もよく見ると瓦が落ちて石垣も一部崩れ・・・現在は復興し見学できます。市長が肝入りで天守をいち早く復興させるって事で早く復興工事がなされました。他の箇所はまだまだですが・・・

宇土櫓も被害が無さそうですが、塀は崩れ外壁もハガレ、建物もただでさえ傾いていたのにさらに傾き、現在は中へ入ることが出来ず、いつ復旧が完了するかも未定だったかな?

最後に桜の馬場でお土産を購入

ちなみに熊本藩の藩校も吉田藩の藩校と同じ、時習館。まだ時習館は他の藩にもありますが割愛。

熊本城を後にします

復興後の天守へはまだ行ってないので、近いうちに行かねばなりませんが、行かなければならない城は山ほどありなかなか行けず・・・
路面電車で移動した先は

地元の居酒屋

地元の料理とビールで乾杯

自己満足でしょうが、ボランティア活動のついでに熊本城へ行き、
ホテルに泊まり、お土産を買い、地元で飲食をしてお金を落とすことが、個人的に出来る1番の復興活動と思ってます。
熊本城その3は、8年前の出来事を熊本地震に絡めてのご紹介となりました。
かなり脱線しましたが、それも城めぐり。
次回、161城目は宇土古城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2024年03月22日
お城めぐり!160城目【田中城】
お城めぐりの160城目は、
静岡県藤枝市にあります、田中城!

田中城は大変面白い城郭です。
円郭式とよばれる縄張りで、本丸を中心に円で何重にも囲われた丸い形のお城です。
個人的には徳川家康が鷹狩するためによく訪れた城で、死因と言われている天ぷらを食し、鷹狩後に田中城へより就寝中に腹痛を起こした逸話のイメージがあります。
城郭の西側(旧東海道側)に城址碑があります。

本丸方面の矢印があります

ところどころ、案内の看板が出ています。

案内に沿って曲がってみると

円郭式だった名残が、今でも道路に反映されており、道が本丸を中心に円状に

本丸は現在、西益津小学校

藩校の教えを引き継いでいるのでしょうか?5の「田中のお城にほこりをもち」いいですね~。「吉田城にほこりをもち」と豊橋市宣言があれば入れて欲しい(笑)

小学校の庭園にはミニチュア田中城が再現

田中城本丸跡石碑

二の門付近で出土した石垣の石も展示


小学校内に田中城主の変遷に

田中城・田中藩の歴史があるのは、田中城教育として素晴らしい!これなら、子供に田中城がどんどん刷り込まれ、自然に知っていきますね。

一部残っている三之堀

三之堀案内

丸い縄張りなのが良く分かります。赤く囲われた部分が残っているお堀です

三之堀の奥に土塁、その奥が三之丸ですが、現在は西益津中学校があります

二之門跡付近に二之堀の一部も残っております




二之堀案内

三之堀の縄張り図と向きが異なるので、図上での場所の確認は要注意!

そして、田中城の南東にある田中城下屋敷へ

専用駐車場があります。この日は夕方だったのもあり、日曜ですが私以外・・・
この時は5年くらい前にて、どうする家康の影響で現在はもっと人が来ているのではないかと思われますが・・・

入口の門がありますが、実は駐車場があるこちら側が裏口です。

整備された庭園

堀跡に

土塁もあります

下屋敷案内図

郷蔵

郷蔵案内

仲間部屋・厩

仲間部屋・厩案内

内部

田中城復元図

建築年月を示す文字。幕末のものですね。

厩!分かりやすく、馬が展示。

茶室

そして反対側の入口へ。こちらが正面かなと。

門の奥には移築された現存の本丸櫓

やはり家康鷹狩の地をアピールしてますね

下屋敷案内図

田中城下屋敷説明

本丸櫓

本丸櫓案内

本丸櫓へ入ります


本丸櫓模型

田中城の縄張り模型

2階へ!やはり急な階段です!


2階にはパネル展示、写真、絵図などが沢山

何度も領主が変わり、時代によって治めた武将が異なるので、信玄・信長・秀吉・家康も田中城へ泊ったそうです。

内部の作りは質素

本丸櫓から入口を見下ろす

庭園を見下ろす

田中城と下屋敷及び本丸櫓をしっかり楽しみました。
本当に丸い形状をしてることを、体感できるのが現地へ行く醍醐味かと思います。
これだけ分かりやすい、円郭式の城はあまりないですし、
お堀や土塁に、現存の櫓まであるので十分楽しめますので、おススメです!
次回は161城目ではなく、震災直後の12城目熊本城(その3)です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
静岡県藤枝市にあります、田中城!

田中城は大変面白い城郭です。
円郭式とよばれる縄張りで、本丸を中心に円で何重にも囲われた丸い形のお城です。
個人的には徳川家康が鷹狩するためによく訪れた城で、死因と言われている天ぷらを食し、鷹狩後に田中城へより就寝中に腹痛を起こした逸話のイメージがあります。
城郭の西側(旧東海道側)に城址碑があります。

本丸方面の矢印があります

ところどころ、案内の看板が出ています。

案内に沿って曲がってみると

円郭式だった名残が、今でも道路に反映されており、道が本丸を中心に円状に

本丸は現在、西益津小学校

藩校の教えを引き継いでいるのでしょうか?5の「田中のお城にほこりをもち」いいですね~。「吉田城にほこりをもち」と豊橋市宣言があれば入れて欲しい(笑)

小学校の庭園にはミニチュア田中城が再現

田中城本丸跡石碑

二の門付近で出土した石垣の石も展示


小学校内に田中城主の変遷に

田中城・田中藩の歴史があるのは、田中城教育として素晴らしい!これなら、子供に田中城がどんどん刷り込まれ、自然に知っていきますね。

一部残っている三之堀

三之堀案内

丸い縄張りなのが良く分かります。赤く囲われた部分が残っているお堀です

三之堀の奥に土塁、その奥が三之丸ですが、現在は西益津中学校があります

二之門跡付近に二之堀の一部も残っております




二之堀案内

三之堀の縄張り図と向きが異なるので、図上での場所の確認は要注意!

そして、田中城の南東にある田中城下屋敷へ

専用駐車場があります。この日は夕方だったのもあり、日曜ですが私以外・・・
この時は5年くらい前にて、どうする家康の影響で現在はもっと人が来ているのではないかと思われますが・・・

入口の門がありますが、実は駐車場があるこちら側が裏口です。

整備された庭園

堀跡に

土塁もあります

下屋敷案内図

郷蔵

郷蔵案内

仲間部屋・厩

仲間部屋・厩案内

内部

田中城復元図

建築年月を示す文字。幕末のものですね。

厩!分かりやすく、馬が展示。

茶室

そして反対側の入口へ。こちらが正面かなと。

門の奥には移築された現存の本丸櫓

やはり家康鷹狩の地をアピールしてますね

下屋敷案内図

田中城下屋敷説明

本丸櫓

本丸櫓案内

本丸櫓へ入ります


本丸櫓模型

田中城の縄張り模型

2階へ!やはり急な階段です!


2階にはパネル展示、写真、絵図などが沢山

何度も領主が変わり、時代によって治めた武将が異なるので、信玄・信長・秀吉・家康も田中城へ泊ったそうです。

内部の作りは質素

本丸櫓から入口を見下ろす

庭園を見下ろす

田中城と下屋敷及び本丸櫓をしっかり楽しみました。
本当に丸い形状をしてることを、体感できるのが現地へ行く醍醐味かと思います。
これだけ分かりやすい、円郭式の城はあまりないですし、
お堀や土塁に、現存の櫓まであるので十分楽しめますので、おススメです!
次回は161城目ではなく、震災直後の12城目熊本城(その3)です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2023年12月27日
お城めぐり!159城目【井田城】
お城めぐりの159城目は、
岡崎市井田町にあります、井田城!

井田城の築城者や時期については不明ですが、
徳川四天王であり、家康の三河平定から五ヶ国時代に吉田城主でもあった、酒井忠次が出生した城として知られております。
井田城は岡崎城から北へ2キロに位置しており、248号線から東に入ってすぐあります。
現在は城山公園として整備されております

1段高いところに公園があります。
廻りの道路はお堀跡でしょうか?

公園内に入るとt広い曲輪だったことが分かります

公園内には城山稲荷があり

鳥居が

奥の稲荷まで

続いております

稲荷の奥には城址碑

その裏側に井田城の伝記が

お隣には白竜大神も建立


お社の脇に説明版がありました

公園から西側を望む。高台にあることが分かります

大樹寺からも近いので、岡崎城とついでに酒井忠次が吉田城へ移る前の居城に触れてはいかが?
次回、160城目は田中城です!
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
岡崎市井田町にあります、井田城!

井田城の築城者や時期については不明ですが、
徳川四天王であり、家康の三河平定から五ヶ国時代に吉田城主でもあった、酒井忠次が出生した城として知られております。
井田城は岡崎城から北へ2キロに位置しており、248号線から東に入ってすぐあります。
現在は城山公園として整備されております

1段高いところに公園があります。
廻りの道路はお堀跡でしょうか?

公園内に入るとt広い曲輪だったことが分かります

公園内には城山稲荷があり

鳥居が

奥の稲荷まで

続いております

稲荷の奥には城址碑

その裏側に井田城の伝記が

お隣には白竜大神も建立


お社の脇に説明版がありました

公園から西側を望む。高台にあることが分かります

大樹寺からも近いので、岡崎城とついでに酒井忠次が吉田城へ移る前の居城に触れてはいかが?
次回、160城目は田中城です!
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2023年12月20日
お城めぐり!158城目【鳴海城】
お城めぐりの158城目は、
名古屋市緑区鳴海町にあります鳴海城!

鳴海城は織田氏の城であったが、桶狭間の戦いの前に、大高城同様に今川氏の支配下になっておりました。
鳴海城をに対するために信長が前回の善照寺砦と他2つの砦を築きました。
鳴海城は現在、鳴海城跡公園として整備されております。

まずは鳴海城近くの東福院へ

こちらの山門、鳴海城の廃材を用いているそうです

古い木材らしきものはあるが、良く分からず・・・でしがた・・・

内側から見ると、しっかり張り紙が!

鳴海城 城門の梁

梁だけでも、古材が残され続けられたことは凄いですね

このめちゃくちゃ細い道は鳴海城跡公園へと続いていました

結構な高低差があることがわかります

これは土塁かな?

左側には平らな部分があるので二の丸かな?

公園入口、本丸の西側虎口ですね

東側虎口

東側虎口前には曲輪らしき藪

堀に見えますが・・・違うかな?斜めにえぐれた窪みは竪堀に見えてしまいます。

小高い丘の上に築かれた鳴海城、駐車場はありません。名鉄の鳴海駅から近いので、歩いていく事をオススメします。
次回、159城目は井田城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
名古屋市緑区鳴海町にあります鳴海城!

鳴海城は織田氏の城であったが、桶狭間の戦いの前に、大高城同様に今川氏の支配下になっておりました。
鳴海城をに対するために信長が前回の善照寺砦と他2つの砦を築きました。
鳴海城は現在、鳴海城跡公園として整備されております。

まずは鳴海城近くの東福院へ

こちらの山門、鳴海城の廃材を用いているそうです

古い木材らしきものはあるが、良く分からず・・・でしがた・・・

内側から見ると、しっかり張り紙が!

鳴海城 城門の梁

梁だけでも、古材が残され続けられたことは凄いですね

このめちゃくちゃ細い道は鳴海城跡公園へと続いていました

結構な高低差があることがわかります

これは土塁かな?

左側には平らな部分があるので二の丸かな?

公園入口、本丸の西側虎口ですね

東側虎口

東側虎口前には曲輪らしき藪

堀に見えますが・・・違うかな?斜めにえぐれた窪みは竪堀に見えてしまいます。

小高い丘の上に築かれた鳴海城、駐車場はありません。名鉄の鳴海駅から近いので、歩いていく事をオススメします。
次回、159城目は井田城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
2023年12月14日
お城めぐり!157城目【善照寺砦】
お城めぐりの157城目は、
名古屋市緑区にあります善照寺砦!

住所は名古屋市緑区鳴海町砦にて、
砦があったことが分かりやすく住所に反映されております。
鳴海町ってところも、鳴海城が近くにあった事がよくわかり、
前回までの鷲津砦、丸根砦は信長が今川氏の大高城に対するために築いた砦ですが、
今回の善照寺砦は信長が今川氏の鳴海城に対するために築いた砦です。
現在はそのままのネーミング、砦公園として整備されています。

その立地や形状は砦を築くのに適した場所だって事が、
今でもよくわかります。
廻りの道路よりも高いことが分かります

下から見上げると階段が奥へ続いており、結構な高低差があります

側面道路から見ると急こう配なのがよく分かります

階段から見下ろしたところ

上部の曲輪から1段下がった小さな曲輪と思われます

階段を登りきると広い曲輪跡があります


奥に案内や説明看板があります



展望台っぽい遊具がありますので登ってみます

あまり高くないですが、遠くは見通せます。遠くに見えるのが鳴海城のあたりか?


南側は攻めてくる今川軍をチェック出来そうです

次回は158城目は善照寺砦が囲う事となった鳴海城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら
名古屋市緑区にあります善照寺砦!

住所は名古屋市緑区鳴海町砦にて、
砦があったことが分かりやすく住所に反映されております。
鳴海町ってところも、鳴海城が近くにあった事がよくわかり、
前回までの鷲津砦、丸根砦は信長が今川氏の大高城に対するために築いた砦ですが、
今回の善照寺砦は信長が今川氏の鳴海城に対するために築いた砦です。
現在はそのままのネーミング、砦公園として整備されています。

その立地や形状は砦を築くのに適した場所だって事が、
今でもよくわかります。
廻りの道路よりも高いことが分かります

下から見上げると階段が奥へ続いており、結構な高低差があります

側面道路から見ると急こう配なのがよく分かります

階段から見下ろしたところ

上部の曲輪から1段下がった小さな曲輪と思われます

階段を登りきると広い曲輪跡があります


奥に案内や説明看板があります



展望台っぽい遊具がありますので登ってみます

あまり高くないですが、遠くは見通せます。遠くに見えるのが鳴海城のあたりか?


南側は攻めてくる今川軍をチェック出来そうです

次回は158城目は善照寺砦が囲う事となった鳴海城です。
いわけん城めぐりマップ
過去の城めぐり一覧はこちら